

|
表紙のリディア、右手にムーンストーンがはまっているのはご愛敬です(こっそり) サンプルは冒頭の2ページ半くらいになっております^^* まだ街中がひっそりと寝静まっている明け方、メイフェア通りに白亜の建物を誇るアシェンバート伯爵家では、人々が静かに、けれど抑えきれない緊張感を漂わせながら、慌ただしく立ち回っていた。 傍らを使用人たちがすり抜けていく気配を神経質に感じ取りながら、リディアは寝間着姿のまま、邸の中でひときわ重厚にかたどられた扉の前で、血の気を失うほどきつく手のひらを握りしめながら立ちつくしていた。 ときおり使用人に指示を求められ、その間だけは我に返るけれど、意識の大半は扉の向こうへ飛んでしまっている。どんな些細な物音も聞き逃さないようにと、じっと彫像のように同じ場所に留まっているリディアの肘に、誰かがそっと触れた。 「リディアさま」 「……ケリー。どうしたの?」 「ハーブティーをご用意しました。少し休まれてはいかがですか?」 「ありがとう。でも、いいの」 もの言いたげな顔をする侍女に、無理矢理作った笑みを向けると、彼女は眉を曇らせた。心配をかけているのはわかるけれど、その気づかいに応える余裕は、今のリディアにはない。 エドガーが邸に運ばれてきたのは、深夜を回ってしばらく経った頃だった。レイヴンが珍しく血相を変えて玄関の扉を開け放ち、その肩に意識を失ったエドガーを支えている姿を見た途端、屋敷は一気にパニックに包まれそうになった。 それを抑えたのはトムキンスで、手早く医者を呼び、部屋の支度を整えたのはハリエットだ。リディアはただ呆然として、彼らが背中を押してくれるまで立ち竦んでいることしかできなかった。 ドクターが来て、屋敷の中は少し落ち着いた。リディアもやっと使用人に指示を出せるくらいには冷静になれたけれど、まだずいぶんと動揺している。邸の女主人としてこんなことではいけないとは思うけれど、震える手を、足を、どうすることもできずにいる。 エドガーを喪ってしまったら、なんて。考えたくないことがずっと頭の中を巡っている。 「……レイヴンは、まだ帰らない?」 邸の主の忠実な従者は、エドガーをここに送り届けて彼の安全が確保されたのを見ると、また外へと飛び出して行ってしまった。犯人を捕まえて参ります、と、リディアに告げるだけの冷静さは保っていたようだけれど。 「はい。ひどく気が立っていた様子でしたけど……」 「ニコが行ってくれたから大丈夫だとは思うけど。……彼まで怪我をして帰ってきたら……」 悪いことしか考えられなくなっている。リディアは言葉を飲み込むようにして口をつぐんだ。大丈夫ですよ、というケリーの気づかわしげな声に、弱々しく微笑んで頷いた。 しっかりしなくちゃ。 気を持ち直すのを支えるように、左手の薬指がぼんやりと熱を帯びる。ムーンストーンがリディアを励ますように光っているのを見た直後、扉の向こうで人が動いた気配がした。はっと顔を上げて、開かれていく扉を凝視する。 静かに開いた扉から出てきた人物に、リディアは胸の前で祈るように手を握った。 「ドクター」 「ああ、奥方さま。こちらにおいででしたか」 「ええあの、エドガーは…………いえ、お茶を、ご用意しますので、そちらでお話を聞かせていただけますか?」 ドクターの気づかうような視線に、リディアはすぐさま詰め寄りたいのを堪えて、ケリーに目配せをした。主であるエドガーが臥せってしまった今、この邸の中で誰が取り乱しても、リディアだけは平静でいなければいけないのだ。 軽く膝を折って動き出そうとしたケリーを、けれどドクターはやんわりと止めた。 「お気づかい痛み入りますが、どうぞこのままで。奥方さま、もう心配はいりません。落ち着きましたのでね。もちろん、しばらくは絶対に安静が必要ですが……弾が貫通していたのが、幸いでした」 「だ、大丈夫なんですね? 本当に?」 「はい」 にっこりと広げられた笑顔でゆったりと頷かれて、リディアはやっと全身に込めていた力を緩めた。一緒に涙腺まで緩みそうになるのを、瞬きを繰り返してなんとか堪える。奥さま、と、ほっとした声を上げるケリーに微笑んで、リディアは傍らで静かに控えていた執事を振り返った。 「トムキンスさん」 「はい、奥さま」 「ドクターに、詳しいお話を聞いておいてください。レイヴンが帰ってきたら、彼にも話を。……あたしは、」 「どうぞ、旦那さまのおそばに。こちらのことはお任せください」 ずんぐりとした身体を優雅に折って、トムキンスが微笑む。リディアは涙が溢れそうになるのを堪えながら小さくお礼を言って、淑女がするには勢いのありすぎる動作で扉のノブに手をかけた。 部屋の中は薄暗くて、毎日使っている寝室だというのに、少しリディアを不安にさせる。 ベッドの近くに備えられたテーブルの上にランプが置いてあるのに気づき、リディアはそっと光量を上げた。眠っているエドガーの負担にならないように、ほんの少しだけ。 震えの残る手のひらを握りしめて、そおっとエドガーに近づく。 薄暗くてよくわからないけれど、顔色が青白いような気がした。目蓋はしっかりと閉じられていて、あまりに深い呼吸に、落ち着いているのだとはわかっていても、このまま起きてくれないのではないかと不安になる。 指先でエドガーの頬を撫でる。前髪を払って、額にそっと手のひらを押し当てた。少し熱い気がするけれど、リディアはむしろ、ひんやりとした感触が戻ってこなかったことに安堵した。 「もう、また無茶して……」 今日、もう昨日になるだろうか。二人で夜会を辞したあと、エドガーはクラブに用事があるからと言って、リディアを邸に送り届けてからまたレイヴンと出かけていったのだ。 離れている間に何があったのかはレイヴンが戻ってこないとわからないけれど、エドガーを喪う恐怖から解放されたリディアは、またエドガーが危ないことに首を突っ込んだのだと決めつけて、目を潤ませながら小さく文句を呟く。 ほんの少しも身じろぎをしないエドガーを覗き込んで、リディアは静かな動作でさらさらの金糸を撫でる。 ゆっくりゆっくり、安らかな眠りを誘うように。 エドガーの髪に指を通しながら、リディアは彼が自分の髪を撫でてくれる感触を思い出していた。とても慎重で、優しい手つき。それはエドガーに愛おしまれているという実感を、どんな言葉よりも雄弁に伝えてくれる行為で、リディアの大好きな仕種だ。 自分の想いも伝わっているだろうか。そんなことを思いながら、手を動かす。 大きな窓に引かれた分厚いカーテンの向こう側では、白々とした朝の光が満ち始めていた。 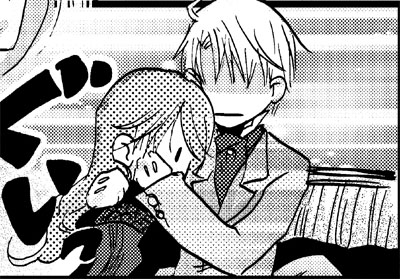 巻末のおまけ漫画の一コマです^^* |

